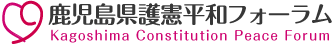村山談話30周年
代表 平井一臣
 今年は、「戦後80年」であり、また「昭和100年」の年にもあたり、マスコミでもこれに関連した特集がしばしば組まれている。しかし、今年が「村山談話」から30年目にあたるということについては、ほとんど注目されていない。ある意味、「戦後80年」や「昭和100年」以上に重要な意味を持つのが「村山談話30年」ではないかと思う。そのことを説明する前に、村山談話とは何か、簡単に振り返っておこう。
今年は、「戦後80年」であり、また「昭和100年」の年にもあたり、マスコミでもこれに関連した特集がしばしば組まれている。しかし、今年が「村山談話」から30年目にあたるということについては、ほとんど注目されていない。ある意味、「戦後80年」や「昭和100年」以上に重要な意味を持つのが「村山談話30年」ではないかと思う。そのことを説明する前に、村山談話とは何か、簡単に振り返っておこう。
1993年、長らく政権与党の座にあった自民党が初めて野党に転落し、非自民の連立政権である細川護熙内閣が成立した。しかし政権内部の不協和音と細川の突然の退陣により政局が流動化し、与党復帰に執念を燃やした自民党は、世間をあっと驚かせる手法をとる。それまで政敵だった社会党(現在の社民党)と組んで政権の奪回を図ったのである。こうして当時の社会党委員長であった村山富市を首班とする政権が誕生した。首相に就任した村山は、それまで違憲としていた自衛隊を認め、日米安全保障条約も容認するという大転換を行い、社会党は混乱に陥る。野党時代に掲げていた政治理念は、政権担当という現実を前に無力だった。
とはいえ、村山としては政権担当中に少しでも「社会党らしさ」を出せないか、苦心もした。その一つが村山談話だった。
「戦後50年」にあたる1995年、村山は国会での決議採択を目指したが、譲歩を重ねた修正文への批判も多く、半数が欠席するなかでの採択となった。この結果を見た村山は、日本による植民地支配と侵略戦争についてのより踏み込んだ内容の談話を発表することとした。村山談話は閣議決定を経て発表されたものであり、政府見解としての重みをもつ。
村山談話については、もう少し前後の文脈と関連づけて見た方がよいだろう。すなわち、宮澤喜一内閣における従軍慰安婦問題についての河野談話、首相就任時の細川護熙による侵略戦争と植民地支配に関する発言など、90年代前半は、かつての戦争に対する謝罪と反省を含む言説が表明される流れがあった。冷戦時代の終焉と55年体制の終焉という国内外の変化のなかで歴史認識をめぐる新たな動きが始まり、この流れのなかで村山談話も実現した。
一方、こうした流れは、自民党内の保守派の危機感を増幅させた。やがて保守派の中心になる安倍晋三が国会議員となるのが1993年であり、村山談話に対する反発と怨念が安倍長期政権下での「戦後70年」の首相談話へと結実した。とは言え、「村山談話」に込められた精神が一掃されたわけではない。「村山談話」を忘却の彼方に追いやるのか、「村山談話」に立ち戻るのか、そうしたことを考えたい今年の夏である。

鹿児島県鹿児島市鴨池新町5−7
電話 099-252-8585